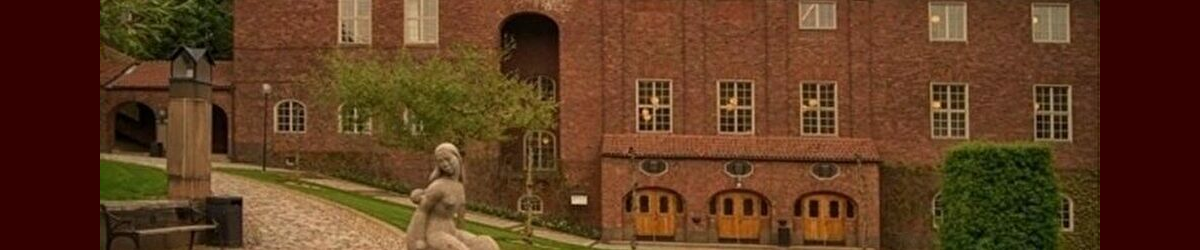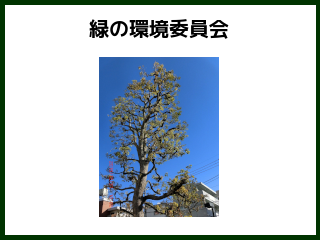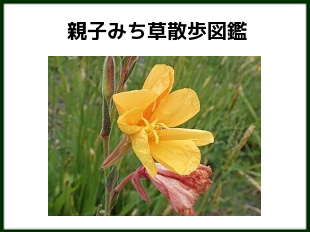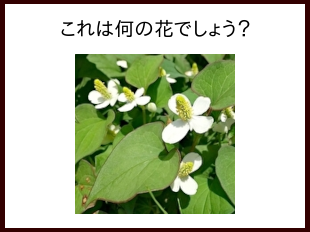手拭いの暖簾(26)朝顔
大輪の朝顔が手拭い一杯に咲き競っています。 いくつもの色のグラデーションに本来ならゴテゴテした感じになりそうにも思えますが、何ともすがすがしく爽やかな気持ちにもなります。 結果私のお気に入りの一枚になりました。 手拭いの […]
山ちゃんの気まま旅35~南紀白浜
毎年夏場に出掛けている南紀白浜へ、二泊三日の海水浴に行ってきました。添付写真は8月1日(日)午後、ワイキキと姉妹ビーチの白良浜です。 コロナ感染のせいか、例年に比べると3~4割ぐらい人出が少ない感じでした。その反面、沢山 […]
手拭いの暖簾(25)江戸切子
色々な用途・形の江戸切子が大判の手拭いに染め抜かれています。 これを見つけるまでは悲しいかな貧弱な知識しか持ち合わせず、小さなコップか小皿の切子しか知りませんでした。 手間がかかり値段も高価な日本の誇るべき伝統芸品を見る […]
フランスあれこれ62~シトローエンは自滅した!
50年位前のことです。人事異動で事務所長が日本に帰国、社用車のシトロエンが残されました。法人スタッフで車の運転は私だけだったので後任が着任するまで私が車の面倒を見ることになりました。お蔭で閑な週末など家族と郊外のドライブ […]
フランスあれこれ61~クロアチアから来たフラミンゴ=私の想い出骨董品(2)
半世紀以上も昔の想い出です。時代は旧ユーゴスラビアの時代、ソ連の影響下にあった共産主義国家でした。日本からの来客がザグレブに到着、それに合わせて空港で落ち合うことにしました。私はミラノから陸路レンタカーを準備しました。 […]
フランスあれこれ60~お酢と油=私の思い出骨董品(1)
我が家の想い出博物館にある一品です。何時の頃手に入れたものか静かに陳列棚に鎮座していますが、これを見るたびに日本の「お神酒徳利」(おみきどっくり)を思い浮かべます。 お神酒徳利は何故か2本、いつも並んで神棚にお供えします […]
山ちゃんの気まま旅34~大阪東部山麓部(2021/04/07)
大阪でのコロナ感染者数急増の折、蜜を避け生駒国定公園の大阪府民の森(交野市)に整備されている「ほしだ園地」をメインに、その後周辺部を散策しました。近くに有りながら、交通の便も良く無いので、地元の人達にとっても不案内の地域 […]
手拭いの暖簾(24)ボストン美術館
からし色の地色にボストン美術館と染め抜かれています。歌舞伎の弁慶と思われる人物が見えを切っている姿と扇子と煙管(きせる)。 江戸時代を思わせる日本。多くの美術工芸品を収蔵しているボストン美術館が日本に里帰りをした展覧会の […]
フランスあれこれ59~戦場(II)ノルマンディー上陸作戦
1944年6月6日、英・米・加・仏などの連合軍がドイツの占領下にあったフランスのノルマンディー沿岸に上陸作戦を決行します。これが決定打となって態勢が一気に収束に向かいました。この現場を一度は見ておきたいと思っていたので […]
フランスあれこれ58~戦場(I)ヴェルダンの戦い
皆さん、アルザス・ロレーン地方という名前はご記憶にあると思います。現在フランスの一部ですがそう言えるのは正確には第二次大戦以降ではないでしょうか。それまでドイツとフランスの間で領土合戦が繰り返された歴史があります。その […]
フランスあれこれ57~ミレーの「落穂ひろい」=バルビゾン村
ナポレオンのフォンテンブローと来ると自然と足の向くのがミレーの「晩鐘」「落ち穂ひろい」のバルビゾン村です。フォンテンブローのすぐ隣り、日本からの旅行者にこの話を出すと皆さん飛びついて是非にと希望されます。しかし現地に入 […]
手拭いの暖簾(23)花蝶々と蔦
箱根美術館のミュージアムショップで見つけた二枚。蝶々が花のようにきれいな色で飛び回っている可愛い図柄の一枚と紺色の何気ない蔦の図柄。 収蔵品は縄文時代から江戸時代に至る埴輪・大きな壺や甕が展示されていました。残念ながらそ […]
手拭いの暖簾(22-1)わらびとふき(追伸)
富貴紙(ふきがみ)について画材屋佐藤紙店から頂いてきたパンフレットから抜粋します。 紙の原料はコウゾ・ミツマタ・ガンピやエジプトのパピルスやバナナ繊維が知られています。この富貴紙は「大蕗の表皮」を原料に作ら […]
手拭いの暖簾(22)わらびとふき
わらびの手拭い。これが暖簾に手拭いを吊るすこととなった一枚です。 その季節には眺めていたい!人さまにも見て頂きたいほどの素敵な色と図柄です。その中にふきも入っています。ふきだけのもう一枚を見つけました。緑色がやさしい柔ら […]
フランスあれこれ56~私のナポレオン(3)ナポレオン追想
1814年ナポレオンは皇帝の座を追われエルバ島に流されて一年、その間戦勝の欧州列国はウイーンで戦後体制を話し合いますが「会議は踊る」で遅々として進まず、後任のルイ18世の悪政による国内の混乱もあって、1815年3月ナポレ […]